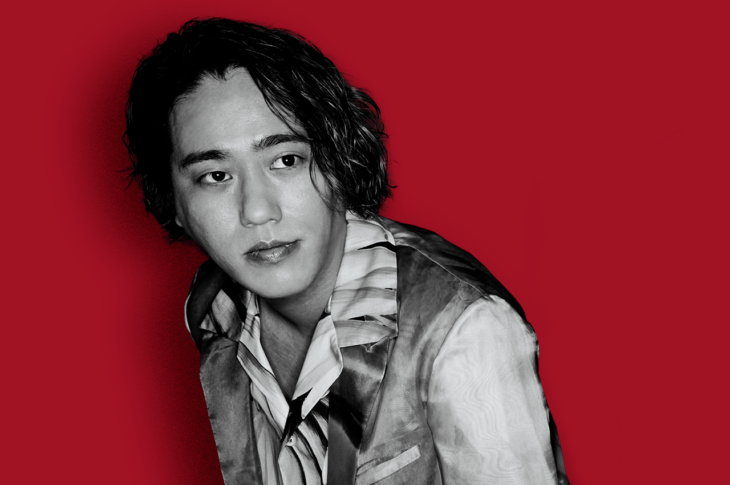PLAYER
同年代のプレイヤーとして長けている人って、
ほとんどがジャズ畑のミュージシャンなんですよ。
━━ショウさん作曲の「オドロボ」についても教えてください。コウキさんとショウさんのデモの形ってけっこう違うんですか?
やっぱり質感が全然違います。特にこの曲はいわゆるポップスではないじゃないですか?
━━トーキング・ヘッズ歌謡というか。
そうですね、まさしく。なので僕もトーキング・ヘッズみたいに16がずっと鳴っているようなものに振り切ろうという提案をして。あとは、ギターにいろいろやってもらいたくて指示しました。自分が好きなBARBEE BOYSとか、BOØWYとか、80年代のバンドの感じは意識しました。
━━「いつも、エンドレス」も「オドロボ」も、“80年代”というキーワードはハマさん発信だったんですね。
もともとすごく好きなんです。世の中的には80’sブームはもう過ぎて2000年代ブームになっちゃいましたけど、2年ぐらい前は韓国勢も含め、けっこうバック・トゥ・80’sな感じだったじゃないですか。そうやって、時代が巡る感じはありますよね。あと個人的に、シティ・ポップ・ブームって“どうでもいい”と言うとちょっと敵を作っちゃいそうですけど……あんまりよくわからないんです。
━━シティ・ポップ、ずっといいですからね。
はい。別にずっといいじゃんって感じなんで。ただ、みんながそれを“いい”って言ってるんだったら、もともと好きだから“寄せていくのもありなんじゃない?”というのはありました。
━━ベース・アプローチはどのように考えました?
「オドロボ」は“ロボット”的なテーマがある曲なので最初ベースは全部打ち込みを想定していたんです。機械的なリフレインのほうが曲のテーマとも合っているし。でも最終的にはそのアイディアはなしになって、プレベで弾いて、音も生々しい感じになりましたね。「いつも、エンドレス」も「オドロボ」もベースは裸っぽいというか生々しい音作りですけど、ライン感があまりに強いようなカッコ悪い“生々しさ”にならないように、塩梅は気をつけました。
━━なるほど。80年代らしい時代感を狙おうとするとシンセ・ベースは自ずと選択肢に入ってきますよね。
シンベも多いし、ベースにずっとコーラスがかかっているのも多いですよね。最初は「オドロボ」もコーラスをかけて録ってたんです。だけどギターやシンセが入って音の棲み分けができてくると、空間系にかかってる実音のまわりにある“膜”みたいな部分が邪魔に感じてしまって、結局は何もかけずに録りました。ビートとベースだけならカッコいいんですけどね。でも今作を通して感じたのは、やっぱりサウンドだけでなくてプレイヤーとしての技量もともなわないとあまり再現性を求められないということです。この手の音楽ってやっぱり、特にドラマーがそういう畑のプレイヤーじゃないとこの感じが出ないところがあって。
━━ジャズやフュージョン畑のプレイヤーということですね。
そうです。あの感じに憧れて今回トライはしましたけど、やっぱ本物は違うっていうか、再現ってなかなか難しいなって思いました。
━━今作の話からは少し離れますけど、近年の日本の、それこそハマさんと同世代のミュージシャンでもジャズがバックグラウンドにあるプレイヤーが増えていますよね。
そうですね。同年代のプレイヤーとして長けている人って、ほとんどがちゃんと音楽学校を出ていたり、ジャズ方面のミュージシャンなんですよ。ロック畑のプレイヤーって本当にいなくて。
━━ハマさんが彼らのことをどう見ているのか、というのは気になります。
そうですね……例えば、昨年頭に木村カエラさんのビルボード・ツアーがあったんですけど、バンマスとしてメンバーの人選を任せていただき、“僕以外全員SANABAGUN.”というバンドでやらせてもらったんです。それでサナバ(SANABAGUN.)のドラムの澤村一平とはiriちゃんとかCoccoさんとかいろいろな現場で一緒にやっているんですけど、彼が言っていたことで印象的なのは、“ロック・アティチュードがわからない”ということで。彼はもともとジャズ・ドラマーでジャズ/ヒップホップの界隈で叩いているので、そういうのをやらせたらピカイチな人なんですけどね。
━━なるほど。
僕はどっちかというと真逆の“ロック派生のブラック・ミュージック好き”みたいな感じなので、お互いのそういうところを補完し合いながらやってるんですが、カエラさんのバンドをやってるときもやっぱりそれは顕著で。サナバのみんなは、スウィングとか16でハネるアレンジとかはすぐできるんですよ。でも「リルラリルハ」とか、いわゆるロック・ナンバーみたいなものは、もう最初みんなド下手で(笑)。もうピカイチのギター・プレイヤーですよ、磯貝(一樹)くんとか。でもその磯貝くんが「リルラリルハ」のイントロの“ジャッジャッジャッジャー”っていうリフを弾けないんですよ。でも、これは本当に悪いことじゃなくて、やっぱりリスナーとして血が通っていることがいかに重要かっていうことですよね。だからみんな適材適所で活躍するんでしょうし。なかには石若駿(d)みたいな満遍なくできる希代のプレイヤーもいますけど、それはきっと聴いてきた音楽とかやってきたジャンルの幅の話なんだって痛感するんです。いくら器用なプレイヤーであっても、みんなが「Johnny B. Goode」を弾けるわけじゃない、みたいな。自分たちを棚に上げるわけじゃないですけどね。
━━ロック出身のミュージシャンにはこの時勢に対して“どうすべきだろう?“って思っている人も多いと思うので、励まされる言葉だと思います。
みんなが“隣の芝は青い”という感じなんだと思います。僕自身、敵対心とまで行かないですけど、斜に構えて“ああいう畑の人たちって、自分たちがやってるようなことに対して「ペンタトニックしか使ってないくせに」みたいな感じなんだろ”って思ってたんですよ。でもフタを開けると向こうは向こうで“あんなことはできない”って逆のことを思っているところがある。それってミュージシャンとして健全ですよね。“あのフィーリングが出せない”みたいなことって、どのジャンルにも共通してある。ちょっと脱線しちゃいましたけど、これは今回自分たちが“年代感”みたいなコンセプトにトライしてみたときにいい意味で痛感しました。その時代に集まった人たちが残した音色っていうのがあるんだなって。
▼ 続きは次ページへ ▼