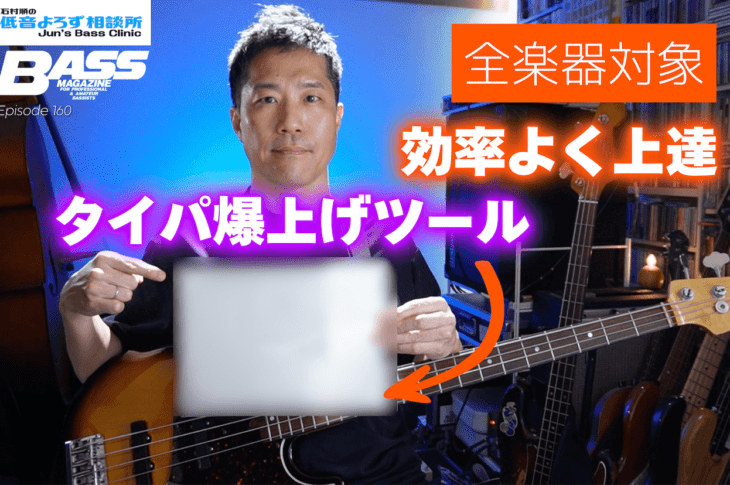NOTES
ドラマー遍歴
田中はこれまで、多くのドラマーとグルーヴを紡いできた。ひょんなきっかけで飛び込んだ東京の音楽シーン。そこには細野晴臣をはじめ、日本のポップ・ミュージックを急速に洗練させていく最先端の音楽人たちがいた。東京で知り合ったドラマーたちは、田中に大いなる刺激を与え、やがて田中も自身のプレイを確立させていく。最初の驚きは、ティン・パン・アレーの林立夫だった。
“林さんのドラムには独特のノリがあって、それまでやってたハックルバックのトン(林敏明)とはぜんぜん違っていた。言葉で言うと“いなせ”な感じっていうのかな。粋な雰囲気が全面に出てた。びっちり合わせたりカチカチに決めたりせず、自由だった。それでも林さんが入ると、サウンドが林さんの雰囲気になるんです。そこがカッコよかった”。
その後、ティン・パン人脈から大瀧詠一との交流が始まり、福生にある大瀧のスタジオで相棒・上原“ユカリ”裕と出会い、山下達郎のアルバムでのプレイをきっかけに、リズム体として業界に認識されるようになる。
“スタジオ仕事に、僕とユカリがセットで呼ばれることが多かった。大仏(高水健司/b)さんにポンタ(村上秀一/d)さんとか定番のコンビも、もちろん活躍されてましたけど、違うタイプのコンビとして声をかけてもらってたように思います。ユカリとは、しっかり音を聴いてキックとかを合わすっていうのではなく、リラックスして好きなようにやってると自然に合っていくというか、グルーヴが盛り上がっていくっていう感じなんです。小さいハネとか細かいところとかが、気にしないでも合ってるんですよ。ほかの人と一緒にやるときは、気をつけないと音の長さが違ってたり、伸ばしたり切ったりとかの細かい部分で、ちょっとギクシャクしたりすることがあるんですけど、ユカリとは気を使わないでできるんです”。
そして松任谷由実との約30年にわたる活動の間、多くのドラマーとの共演を果たしてきた。
“ドラムはけっこう変わりましたね。最初は風間幹也くん、それから菊池武夫さん、その後は江口信夫くん、村石雅行くんと変わって。宮田繁男くん、それで小田原豊くんになるのかな? 全員タイプが違うからおもしろかったな。やりやすさとかは曲によりますね。ノリが合ったときは、相手が誰であれ気持ちいいグルーヴが出てたし。村石くんが一番トリッキーでしたね。僕、ジャズはあまりやらないんで、ジャズのエッセンスが入ってるような曲とかでは、彼とのコンビが一番刺激があっておもしろかった。いちばんロックなのは小田原くんです。彼とやると気持ちいい。いいところにキックがハマってくる。自分が来てほしいところに来る。微妙なタイミングだから聴いてる人はわからないと思うけど、一緒にやった僕だけの感覚です。まあ人間と人間ですから”。

●●●
田中章弘は無骨なミュージシャンだ。器用なタイプではないと周囲も口を揃える。器用なミュージシャンというのは音楽の進化や変化への対応力に富み、短時間に一定水準以上の演奏をこなし、現場で重宝される。一方で田中は、器用ではないという評価を受けながらも、なぜか(失礼!)日本のポップ・ミュージックが進化していく、その最先端で重用され続けてきた。これはどういうことか。つまり一流の音楽には、音楽それ自体の進化や変化に対応することとは別の文脈で、普遍的なサムシングが必要だったことを示している。それこそがグルーヴだ。田中のベースにはそれがあった。しかもとびきり骨太のやつが。
同じ譜面を渡されて、仮にそれが、誰もが弾けそうなシンプルなラインだったとしても、グルーヴが出ているか否か、出ているならどんなグルーヴが? 違いはそこに出る。グルーヴは曲の呼吸だからだ。譜面では絶対に表わすことのできないそのニュアンスは、しかし決して微妙なものではなく確実に存在し、耳と全身の毛穴から人間の潜在意識にすべり込む。まるでウイルスのように。そして人々のアドレナリン分泌を促し、原因不明のワクワク状態にさせる。もしワクワクするビートに出会ったらパーソネルを調べてみてほしい。“ベース:田中章弘”とあったら、原因のひとつはそれだ。