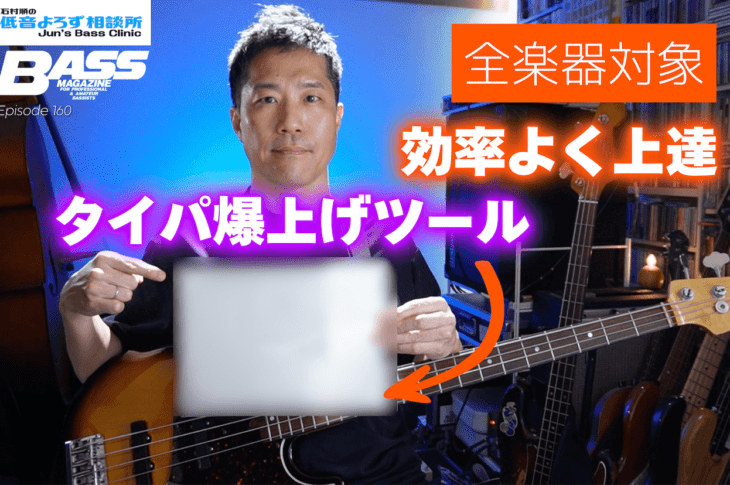NOTES
華麗なる人脈リレー、そして「BOMBER」
唐突に響く工事現場のドリルの音。そして上原によるタイトなスネアが4拍。直後に、普段は穏和な田中が、愛器プレシジョンで獰猛な咆哮を上げる。この「BOMBER」のオープニングにおけるベース・ラインこそ、ミナミはアメ村(心斎橋の一角)のサーファー・ディスコで、談笑するカップルの尻を蹴り上げ、強制的にダンスフロアに導く要因となったフレーズだった。
“達郎さんからは「スラップで」って注文でした。譜面にタマ(音符)は書いてなくて、DmとかGmとかコードだけ。僕がああいうフレーズを弾いてみたら、達郎さんが「じゃ、これで行こうか」って。一発録り(全員による通し演奏で、修正やダビングなし)で3回やったのかな? だからリリースされたトラックは、3回やったなかのベスト・テイクです。“せーの”でやって、達郎さんが仮歌を歌って、ユカリが近くでドラム叩いて、ギターの椎名(和夫)くんがブースにいて、キーボードは難波(弘之)さん。懐かしいなあ”。
そして、2番の歌が終わり、のちに伝説となるベース・ソロが炸裂。田中のほかには相棒・上原ユカリが叩くシンプル&タイトなドラムのみだ。
“ベースが張り切ってるような曲だったんで、ソロ入れたらいいんじゃない?みたいな雰囲気に自然となったんだと思う。で、指が勝手に動いちゃってああいうラインになった。まあ曲自体が良かったからね。曲がいいとノるでしょ? モチベーションが上がって、いい方向に転んだんだと思います。録音が終わったあと、みんなで盛り上がりましたしね。あとで(吉田)美奈子さんがコーラスのかぶせ(ダビング)をしたとき「いいじゃん、このベース・ソロ」って褒めてくれたんで嬉しかったです”。
このたったの8小節が、大阪中のサーファーのハートをわしづかみにした。やがてそれが全国に広がり「BOMBER」は、山下達郎をメジャーに押し上げる記念すべき曲となった。
“ツアーで大阪に行ったとき、そのサーファー・ディスコに行ってみたんですよ。DJに挨拶したら、僕が来てることをみんなにアナウンスしてくれて「BOMBER」をかけてくれたんです。そしたらみんなが寄ってきて「あのベース、あんたがやったん?」「あんたが弾いたん?」って。で、「あれ、めっちゃええやん!」って言ってくれてね。嬉しかったですよ。そのDJ、ファンク系の音楽が好きで、この曲を気に入ってヘヴィロテでかけてくれてたんです”。
この8小節は、もちろんサーファーだけでなく、若いアマチュア・ベーシストたちからも熱烈な支持を受けた。このソロで田中のことを初めて認識した者も多かった。
“なんか噂になったらしくて「大学時代、サークルでやりました」とか「昔、必死にコピーしました」とか言われて。ただ「あのライン、どうやってるんですか?」とかも、よく聞かれたんです。こっちもわからないけどね(笑)。自分でワケがわからないところが功を奏したんでしょうね。でも、あとからステージで弾くときは苦労しましたよ。音源聴きながら、自分のフレーズを必死にコピーして(笑)”。
音質的にも、目の詰まった1969年製プレシジョンのサウンドが前面に押し出され、ベーシストのなかでは大きな話題になった。プレベらしい丸くウォームな音質でありながら、ひとたびグルーヴさせると、こんなにも人をワクワクさせる、ぶっといパルスを発生させるのか、と感じさせるようなサウンドだった。
“吉田保さん(著名エンジニア、吉田美奈子の兄)が録音したんですよ。僕は卓(ミキシング・コンソール)に直結だったけど、卓のほうでコンプをかけてくれたんじゃないかな。独特の音をしてますね。プレシジョンのすごくいい状態の音。その組み合わせでできたんだと思います”。
曲の良さに演奏者の技量、楽器の音、録音などあらゆる要素が組み合わさり、田中が考えていた以上の出来になったのがこの「BOMBER」だった。録音の現場では、こうした化学反応がたまに起こる。
“そう、偶然ですよね。すごいものを作ろうって思って演奏しても、なかなか思いどおりにはならない。でも力を抜いてやっても、偶然みんなのいいところが引き出されて、すごい気持ちいい音楽になっていく。そういうことが、たまにある。「BOMBER」なんて本当にその典型的な例だと思います”。

山下達郎のアルバム『SPACY』(1977年)と『GO AHEAD!』(1978年)、『MOONGLOW』(1979年)に参加した田中は、上原とともにサポート・バンドを脱退してしまう。
“達郎さんの音楽も変わってきて、自分でも納得いかないプレイが出てきて。やっぱり何か違うなって感じてました。達郎さん自身もそう感じたんじゃないかな”。
そしてリズム体は伊藤広規(b)と青山純(d)に変わる。ふたりはハックルバック時代の田中の盟友・佐藤博(k)が率いるハイ・タイムズにいたメンバーだった。そして山下達郎は大ヒットを連発。その様子を田中はどんな思いで見ていたのだろう?
“曲が急にポップっていうか、スケールの大きなメジャー曲って雰囲気に変わりましたよね。曲も良くて、これは売れていくなって気がした。新しく入った広規のベースと青山のドラムについては、サウンドに合ってるなあって思いました。広規については「おー、カッコいい!」ってのが第一印象。自分にはできないなって思った。同じチョッパーでもやり方が違うし、弾き方も違うし、音の作り方も違う。僕はプレベで彼はジャズべだしね。僕だったらもっと泥臭いプレイになってたと思いますね”。
山下達郎のもとを離れ、ふたり同時にスケジュールが空いた田中と上原によるリズム体。それを、噂に敏感なスタジオ業界が放っておくはずはなかった。
“僕とユカリのセットで1日3本くらい、いろんなスタジオを回ってました。もちろんユカリと別々にもスタジオの仕事はいろいろやりました。それで高中(正義/g)と知り合って、彼に誘われて彼のアルバムに参加することになったんだと思います”。
高中正義は、『JOLLY JIVE』(1979年:ベースは高橋ゲタ夫)の成功でノリに乗っていた。だからこそ、その後のアルバム制作には熱が入っており、メンバーへの要求も厳しかった。レコーディングは伊豆にあるキティのスタジオで、合宿しながら行なわれた。高中はリズムに敏感だった。出来の良し悪しではない。自身の思い描くビートが鮮明に頭のなかに存在し、そのイメージとのギャップが少しでもあると、決してOKを出さなかった。テンポやアレンジが指定どおりであっても、全体が組み合わさったうえで生まれるベクトルがズレていると、高中は演奏を止めた。
“合ってなかったら「合ってないじゃん」って。僕はそれほど言われなかったけど、厳しく言われてたメンバーもいた。全体のノリですよね。自分の世界じゃなかったら、作っても意味がないという。そのへん彼は、はっきりしてましたね”。
高中のアルバムがヒットした要因として、ポップなメロディ・ラインをあげる者は多い。だが裏側に、そのメロディを最大限に生かすアンサンブルがまわりを固め、聴く者をワクワクさせるようなグルーヴが寄り添っていたのも事実。だからこそ高中の弾くメロディが、より際立ったのだ。
“高中自身もギターうまいしね。というかノリがすごくいい。独特ですよ。それで音が太いんです。音の細いギタリストがチャラチャラ弾いても、ああいう感じには絶対にならない。それに彼は自分のスケールを持ってる。高中スケール。あれ聴いてると、こっちも明るくなるし、楽しくなる。僕は好きですね。厳しかったけどおもしろかった。すごく印象に残るレコーディングでした”。
その後は寺尾聰のツアーで武部聡志(k)と知り合い、ほどなくして武部が音楽監督を務める松任谷由実のサポート生活に突入。あるときは嵐のなか避雷針のごとく、ひとり高所で暴風に煽られながら、またあるときは噴水で全身を水浸しにしながら、一定のグルーヴをハズすことなくベースを弾く、といった約30年間にわたる生活を送ったのも本篇に書いたとおり。武部とともに、ユーミン・ワールドを彩り続けた。
“ユーミンの曲って、アルバムのアレンジは松任谷(正隆)さんだけど、ツアーでは松任谷さんは演出に回るから、ライヴ用のアレンジは全部、武部さんがやる。エンディングはもちろん、曲間のつなぎとか、ユーミンが着替えてる間の場面転換の部分とか全部ね。ユーミンのステージはショー仕立てだから、アルバムに入ってないことをやる時間がたくさんあるんです。曲自体のアレンジもアルバムとは違うし、考えなきゃいけない部分が多い。だから武部さんは相当努力してると思います。すごいですよ”。