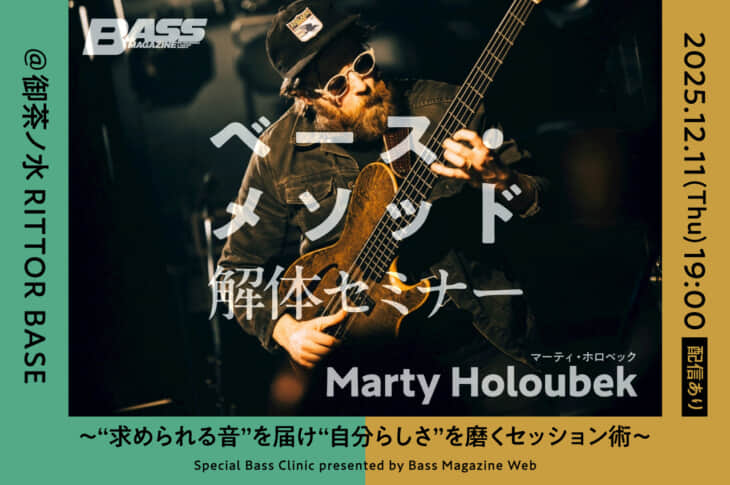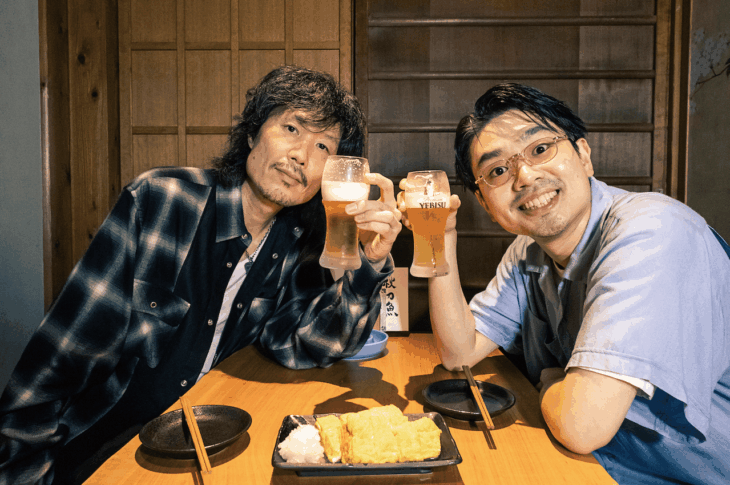SPECIAL

UP
FEATURED BASSIST-あきらかにあきら[THE ORAL CIGARETTES]-前篇
- Interview:Takahisa Kondoh
- Photo:Satoshi Hata(P.2)

今起こっている出来事があるからこそ
今後、生まれる曲が絶対ある。
──本作を制作している頃はまだ今のような新型コロナウィルスの問題は生まれていなかったと思うんですが、結果的に今の時代とリンクするような世界観の作品になっている気がしました。
まさにそうなんですよね。今作は意図せず、生命とか地球とか、そういった世界観の作品になって。地球規模の生死に関わる問題と直面しているこの現実のなかで、何かしら考えざるを得ない世界になってますけど、僕らにとっても、もう一歩踏み込んでより広がりのある世界観を提示するタイミングだったんです。これもあくまで僕の考えなんですけど、“音楽でハッピーになろうよ!”みたいな考え方も全然アリだと思うんですけど、僕らはやっぱり現実を直視してしまうし、今後、今起こっている出来事があったからこそ生まれる曲も絶対あるだろうし。無責任には表現できないなっていう思いもあるんですけど、偶然ながら、そういったことがすべてリンクしたと思います。
──では、今作を制作する際に考えたことは?
まずは今作を作るにあたって“エンターテインメント性”についてメンバーと話し合っていたんですよね。世界規模のトップレベルのアーティストとか、国内でもアリーナやドーム規模で活動しているアーティストのライヴを観たとき、ショウとしての流れというか、“波”みたいものに対して美しく感じることが多くて。例えば、冒頭はテンションを上げて、そこからちょっと心地良くなって。で、不安にさせたりしつつ、でも最終的には幸せ、みたいな。ひとつのライヴのなかで、そういった“波”を作りたいっていうことをみんなで考えていたんです。で、去年のフェスなどでそれを実践してみたんですよね。でもやっぱり30分や40分の長さのセットリストだと、なかなか伝えきれないっていう思いもあって。加えて、“オーラル、ちょっと変わったな”とか“もっとアゲアゲやったんちゃうん?”みたいな声もあったし。そこで改めて“これはバンドとしての表現方法を、もっと明確に提示していかないといけない”って感じたんです。そこで、アルバム一枚のなかで表現の緩急をつけよう、と。結果、このヴォリューム感と、波のある流れになりました。あとは、盛り上げ上手なイキのいい若者はどんどん出てきているので、僕らはちょっと貫禄も見せないと(笑)。
──今、フェスっていうキーワードも出ましたが、昨年9月14日、15日に泉大津フェニックスで行なわれた“PARASITE DEJAVU ~2DAYS OPEN AIR SHOW~”で目に焼き付けた風景も、作品作りに影響しているのでは?
それはめちゃくちゃあります。あのイベントの1日目(DAY1 ONE MAN SHOW)はワンマン・ライヴ、2日目(DAY2 OMNIBUS SHOW)は今までずっと一緒にやってきた仲間と対バンするっていうコンセプトだったんですけど、過去に自分たちがやってきたことを肯定できたり、目の前にいるお客さんからの愛情をすごく受け取ったんですね。“ここまで愛されているなら、そしてお客さんやバンドマンの仲間との信頼を築きあげられたなら、軸や芯はもはやブレないだろうし、どんなものをどんな形で届けようとも、僕らが証明して見せることで、変な勘違いや誤解はされないだろうな”っていう確信になって。あとは、ファンクラブ・ツアーも僕のなかでは大きかったです。僕らのことを思ってくれている人たちが全国でこんなにいるんだってことを感じて。だったら、もっと大きく進んでいこうぜみたいな感じでしたね。
曲に対するアプローチに関して
頑固になっていてはいけない。
──ちなみに、ワンマン・ライヴとフェスや対バンでは、意識することに違いはあるんですか?
ひと言では言えないんですけど、フェスだったら、とにかく“俺らカッコいいだろ! ワンマン来たいだろ!”みたいに、めちゃドヤってますね(笑)。
──うはは、最高ですね(笑)。
なぜなら、僕個人というよりも、フロントマンの拓也(山中拓也/g,vo)を筆頭に、メンバーみんなのカリスマ性が高いので、例えばフェスで一度でも目に止まってもらえたら、しっかり心を掴めるんじゃないかなって思っているんです。結果、フェスではわりとドヤっています(笑)。ただ、ワンマンのライヴだと、お客さんとのお互いの信頼感があるというか、もっと愛情が深くなるというか、ライヴを一緒に作っている感覚はありますね。そして、お客さんもみんなドヤっててくれればいい(笑)。結果、みんなドヤってるのか? みたいな感じなんですけど(笑)。ただ、最終的には4人から広がっていくパワーが大事なので。4人の息が合ってないと、いくらドヤってもカッコよくないし、メンバー同志の意思疎通が大事かなっていうことはいつも強く思ってますね。
──今作については、どのような意識で作品作りに取り組みましたか?
言い方は難しいんですけど……やはり作詞/作曲者が考えている意図に忠実でないといけないとは常に思っています。拓也の場合は筋が通っていて、軸がブレてないので、そういった信頼感があるからこそなんですけど。例えば、フロントマンがヌルい空気でやっていたら、“忠実にはなれません”ってなると思うんですけどね。そういった前提があるなかで、その曲に対するアプローチに関して頑固になってはいけないなって思うんです。今回はその思いが特に強かったですね。曲のイメージを優先して、もはやベースを弾かないでベース・シンセを取り入れた曲もありますし。特に今作は、歌詞についても筋が通っていて深いことは、声を大にして言いたくて。歌詞の世界観が、サウンドに影響する部分はかなり多いので。
──今作の楽曲を聴いて、アンサンブルのなかでのベースの立ち位置がより際立っているように感じました。
確かに今回、ミックスの段階から “これだけベースを聴かせてくれるんだ!”っていう驚きがありました。もともと、僕らリズム・セクションが大事だなとは思っていましたけど、今作のミックスを聴いたときに、耳に入る位置にベースの音を置いてもらっているなって感じたんです。そういうところから、良いベースが弾けたんだなって思えました。
──そうなった理由は?
基本といえば基本なんですけど、楽曲に対するアプローチとしては、しっかりポケットに入れていくことに加えて、かっちりしすぎないグリスだったりとか、そういったニュアンスを気持ち良く入れていく作業ができたことが大きいと思いますね。
▲インタビュー後篇は5月26日、Bass Magazine Webにて公開予定!▲
【Equipment】
▼ あきらかにあきらからの重要なお知らせは次ページへ ▼