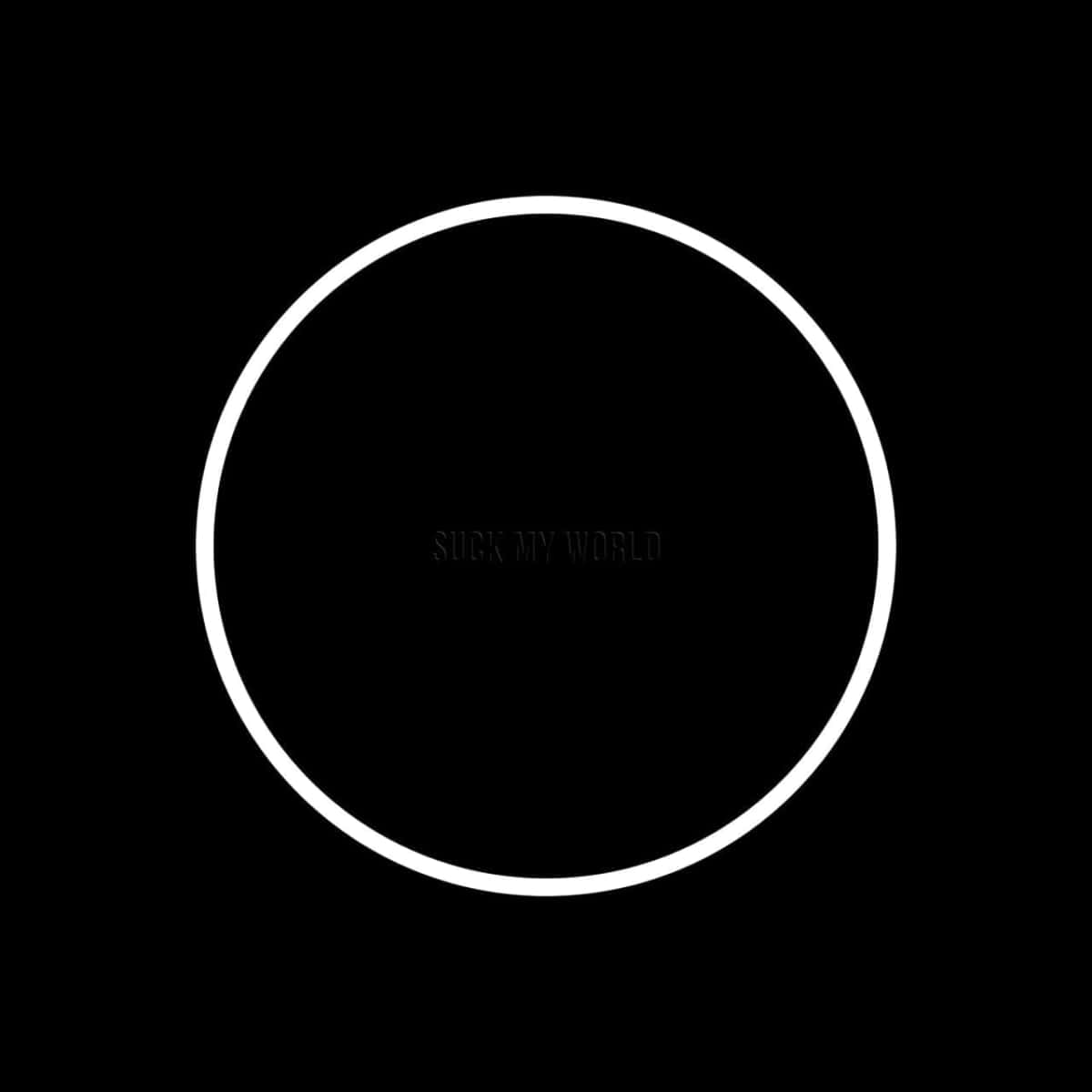SPECIAL

UP
FEATURED BASSIST-あきらかにあきら[THE ORAL CIGARETTES]後篇
- Interview:Takahisa Kondoh
- Photo:Satoshi Hata(P.2)
新たな道を切り拓くベーシストの視点:後篇
4月に5thアルバム『SUCK MY WORLD』をリリースしたTHE ORAL CIGARETTES。先日公開したインタビュー前篇に引き続き、ベーシストのあきらかにあきらから、作品作りを通じて得たベーシストとしての成長や、次世代ベース・ヒーローとしての野望について話を聞いた。
Interview
力が抜けた状態で弾くことで、
鳴っている音楽と同化できる。
──インタビュー前篇では、楽曲のアプローチとして、かっちりしすぎないグリスなどのニュアンスを、気持ち良く入れていく作業ができたという話がありました。その気持ち良さを掴んだきっかけはあるんですか?
「Fantasy」のレコーディング中に、プロデュースしてくれた方から、“お酒を飲んだときの感覚を大事にすればいい”っていう話を聞いて、なんかちょっと掴んだ気がしました(笑)。
──なるほど。酩酊する感覚が大事っていうこと?
もちろん、飲酒を薦めているわけじゃなくて、酔っ払うと誰でもそうですけど、リラックスしてきて、ちょっとゆらゆら揺れたりするじゃないですか。そんな風に、何も考えずに感じたまま自分の体を動かしたり、力が抜けている状態が大事で。で、その状態でベースを弾くことによって、一緒に鳴っている音楽とより同化できるっていう感じですね。で、“このフレーズを必ず弾くんだ”とか“考えてきたこのフレーズを弾かなければいけない”などではなくて、フレーズは一旦置いておいて、ノリに身を任せて出てきたプレイこそが、その曲に合うベースなんだっていう。
──あくまで楽曲から受ける雰囲気を大事にする、と。
そう。素直になるって感じですね。だから今回も“デモで弾いていたものを必ず弾かないといけない”みたいな意識はなくて。逆に、レコーディング中に生まれたフレーズも多いんです。そういう意味では、よりライヴ感があったのかもしれないですね。
──シラフのままで、その音楽に浸ることができたら最高ですね。
そうそう。だから別にお酒は必要ないんですよ。お酒がなくてできたら最強なので。あと、少し前に、黒人のリズム感に関する本を読んでいたんです。ダンサー向けの本だったんですけど、体全体をしならせて踊ることが大事だということが書いてあって。加えて、自分自身がメトロノームになって、鳴っている音楽と一緒に合わせるっていう意識によって気持ちよくなるっていう考え方があって。それを読んだ時点では理解しきれてなかったけど、今作のレコーディングで、“こういうことの延長にあるんだな”って、少し背中が見えた感じではありましたね。
──レコーディング中の、どのあたりでそれに気づいたんですか?
レコーディングの中盤くらいですね。それからは、ポケットをより意識するようになったし、その曲のベースのフレーズやリズム・セクションを見るだけじゃなく、曲全体の雰囲気を感じてからレコーディングに臨むようになって。レコーディング当日は、みんなで意見を出し合いながら、その場でディレクションしてもらいつつ僕が弾くっていう感じになっていきましたね。それがめちゃくちゃ楽しかったです。もちろん、指図されている感じでもなくて、プレイがキマったらハイタッチ、みたいな。“それそれ”“これか!”っていうやりとりがあって。
──あと、ベース・プレイについて意識が変わったきっかけは?
去年のツアーが終わったぐらいから、自分のリズム感をより極めないとって思い始めていたんです。それから、先ほど話題に出た、本を読むことにつながっていくんですけど、例えば音価のコントロールや、8分のノリひとつにしても、バスドラに合わせるのか、それともスネアを感じるのか、とか。そういった細かい視点をライヴで補正していく作業があったんですね。特に去年の夏フェスの時期あたりに、自分のなかで意識改革があって。それとは少しさかのぼりますけど、2018年11月11日のベースの日のイベント(“THE BASSDAY LIVE 2018”のこと)に参加したことも大きいです。名うてのベーシストたちと同じ土俵で戦うのは怖かったけど、でも逃げたくなかった。結果、参加したことで悔しい思いもして。そこから自分のなかでもうひとつ上に行かないとって思ったんですよね。そういった取り組みをしていたなかで、楽曲ごとのアプローチも、より細かく突き詰めていったんです。