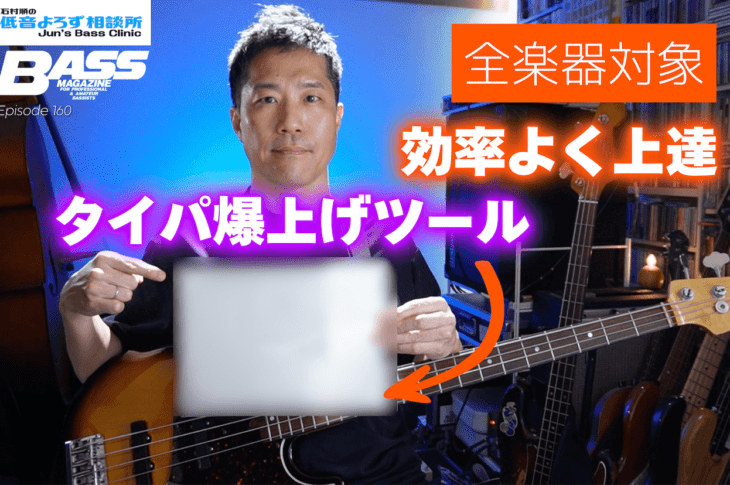NOTES
修行は、自覚と覚悟を生み出す
六川を知る音楽仲間はみな“六さん(六川のニックネーム)はいろんな音楽を知っている”と口を揃える。ピーナッツから始まり、ベンチャーズやビートルズ、そして来日した膨大なアーティストたち、それらを六川はどんどん吸収していった。特筆すべきは、ほとんどが能動的な行動によることだ。特段、音楽的な環境に恵まれていたわけではないサラリーマン家庭の長男にとって、自分から動かずに新しい音楽を得ることは不可能だった。
しかしそんな六川にも、強制的に音楽の海に叩き込まれるという機会が訪れる。合歓の郷での修行がそれだ。ヤマハが運営する合歓の郷で、これから世に出るシンガーたちのバックを日替わりで務めるというハードな日々は、まさに修行と言える半年だった。
“まだヒットを出す前の松崎しげるさんや庄野真代さんとか葛城ユキさんとかのバックをやるわけ。書き譜の嵐で、すごいプレッシャーだった。フラットが4つ(A♭キー)あると、どこがフラットするのか?とかね。半年くらいだけど、この時期に集中してやった。濃かったですね”。
六川は、仕事だからと自分を追い込んだ。悲壮感を持って臨んだというより、今の自分に必要だという強いモチベーションがあった。
“バンドだったら譜面なんていらないけど、僕はベーシストとして、ひとりで生きて行こうって気持ちがあった。それには譜面が読めることが必要だなって考えたんです。最初はぎこちないけど、だんだん体に入っていった。こういうことなんだって確認しながらやってた。音楽学校に行ってたわけじゃないから、自分でやるしかないじゃないですか。逃げ帰るわけにもいかないし。おかげで譜面が読めるようになったし、初めての人とプレイするとき、あんまりビビらなくなりました(笑)”。
合歓の仕事が住み込みだったことも功を奏した。音楽に集中しやすい環境で、資料室にはレコードや教本などが豊富にあったからだ。もともとR&Bが好きだった六川にとって、この時期に勃興したクロスオーバー・ムーブメントは大好物。ジャズの洗練された音使いとソウルのハジけるようなグルーヴが結びつき、R&Bは急速に洗練されていった。六川はそれを貪るように咀嚼し、血肉化した。
“レコードは片っ端から録音して部屋で聴きまくった。それとモータウンでベースを弾いてたキャロル・ケイの教則本があったんですよ。あれはあとで買い直したくらい役に立った。今も取ってあります。いろんなジャンルのパターンが書いてあってね。普通の教則本と違うのは、モータウンのパターンを想像させるような8ビートとかレゲエとかが書かれてたこと。この本を知ったことによって、レコードの聴き方も変わってきました”。

この時点でベースを始めて3〜4年しか経っていなかった六川だが、合歓の郷から戻ってきたときには、早くもベースを教える立場になっていた。
“軽音楽部でバンドやってただけで、音楽学校なんて行ったことなかったんだけど、ヤマハの恵比寿にあったネム音楽院でベースの先生をやってくれって頼まれて、1年間やりました。その頃はクロスオーバーが流行ってたんで、それを譜面に起こして生徒に弾かせたりとか、そんなことしてた。生徒になんとプリズムの渡辺建(b)ちゃんがいてね。彼、すでにプリズムやってたのに習いにきてた。すごかったですよ、当時のネム音楽院って。優秀な生徒が多くてね。建ちゃんなんてダントツにウマいから、僕のほうが逆に「アルフォンソ・ジョンソンのフレーズ、教えてくれない?」とか教えてもらったりしてた(笑)。そしたら建ちゃんがね、雑誌のインタビューで「あなたの恩師は誰ですか?」とか聞かれて「六川正彦さん」って答えてくれたところまでは良かったんだけど、そのあと「エヘヘ」とか書いてあるの。笑ってるんだよね(笑)”。
ベースを始めて1〜2年でプロを目指し、4年目で教える立場に立つというのは一見無謀にも思えるが、六川にはそれまでに蓄積した膨大な音楽の知識があった。そして何より、ドラムの経験により、ビートの本質を肌で理解していた。この時期、つまり1970年代半ばの日本で、大きなうねりを見せていたのがニューミュージックと呼ばれるポップスだった。六川はその大きな波に飛び込んで、南佳孝、吉田美奈子、あがた森魚などと共演し、ベーシストとして本格的なキャリアを積み上げていく。
“いいタイミングで、ニューミュージックが盛り上がったんです。それまでグループ・サウンズの時代があって、ニューミュージックが出てくる時期が、大学を卒業する時期に重なった。駒沢さんはすでにニューミュージックの世界で活躍してて、そのあと僕も引っ張ってもらって、一緒にやるようになった。それでニューミュージックの世界に引き込まれていったんです”。
きっかけは駒沢の誘いだったが、ミュージシャンの溜まり場だったギャルソンや下北ロフトに入り浸るうちに、次第に六川は周囲から認められ、さまざまな仲間から声がかかるようになる。
“吉田美奈子と一緒にやったのもその頃。美奈子は自分のことをボクっていうんだけど、ある日ギャルソンで会ったとき「ボクとやってみる?」とか、そんな感じで誘われた。それで当時やってたバンドのメンバーで美奈子のバックを務めたんです”。