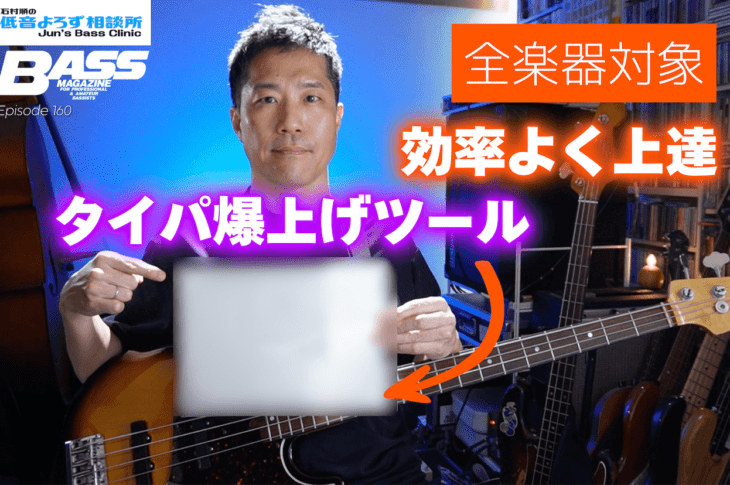NOTES
行動は、進むべき道を照らす
高校では、グループ・サウンズに憧れ、ゴーゴー喫茶に通うようになり、そこで間近で観られる生演奏にハマる。生のステージではテレビで観られるオリジナルのシングル曲ではない、洋楽のカバー曲を観ることができ、六川は生演奏の熱気だけでなく、楽曲自体の魅力にも気づかされる。
“彼らのカバー曲が気になるようになってきてね。ツッパリの同級生で、シュープリームスとかジェームス・ブラウンとかが好きなやつがいて、そいつの家に行ったらモータウンとかスタックスとかのレコードがあってね。それで高校が歌舞伎町に近かったから、アップルっていうゴーゴー喫茶に、親に内緒で行くようになった”。
ゴーゴー喫茶は、行くだけでなく、ついにバイトまでし始める。そこに出演するグループのステージが無料で観られるからだ。これも六川らしい行動力のひとつ。
“ゴールデン・カップスはほかと違うという感覚があった。今でもそう思ってるけど、外タレみたいに思ってました。マモル・マヌー(d)さんのあのシェイク・ビートとかが大好きでね。そういう基準で聴いてたから、途中から趣味が外タレのほうに移っていっちゃった”。
グループ・サウンズは六川にふたつの影響を与えた。ひとつは、彼らがソウルやR&Bのカバーをしていたことで、洋楽に目覚めたこと。もうひとつは、ルイズルイス加部や柳ジョージのプレイする姿に憧れ、それまで担当していたドラムから、ベースというパートに興味を持ったことだ。そこには、ジューク・ボックスから流れてくる大音量のR&Bの影響もあった。
“ジェームス・ブラウンやスライ&ザ・ファミリー・ストーン、モータウンやスタックスとか、ソウル系が多かった。サザン・ソウルやR&Bを聴きまくったのはその頃でしたね”。
ベースは、見た目的にはルイズルイス加部の弾く姿に憧れたが、音楽的にはドラムと一緒にグルーヴを作っていることを無意識に感じ取っていた。
“それまでドラム寄りだったのが、加部さん観た瞬間からベースの魅力にハマっていった。「ベースやろうかな」っていうより「ベースってカッコいいんだな」って感じかな。なぜかギターには目がいかない。ギターが花形と言われてたのに。なんでだろう。きっと普通じゃないんだね、僕は。ドラムやってたせいか、音楽的にはベースが一番近い存在だったからかな。ギターも買ったんだけど全然ハマらなかった。やっぱりビート感っていうか、ジューク・ボックスから聴こえてくるビートがカッコ良かったからでしょうね。ジェームス・ブラウンとかサム&デイヴとか”。
そんな日々を過ごすうち六川は、自然と音楽の道を目指すようになる。親戚に音楽家がおり、少しはその血を意識していたのかもしれない。
“母方の親戚に音楽家の夫婦がいてね。オーケストラでチェンバロを弾いてる叔母さんとその旦那さんがクラシックの指揮者やってて、神戸に住んでたんですけど。お袋が「一度行ってきなさい」って言うから、新幹線に乗れることもあって、喜んで行ったんですよ。そうしたら、いきなり説教が始まっちゃって。「正彦、お前ベンチャーズとかロックとかやってるんだって?」って言うから「はい」って答えたら、即座に「あれ、音楽じゃないから」だって(笑)”。
高校で音楽にどっぷりハマっている息子を目の当たりにして、将来を危惧した母親が親戚に相談し、音楽への道を諦めさせようと画策していたのだった。
“なんか裏でそういうことになってたみたいで(笑)。お袋がロックとかそういうの反対してたんです。言われた瞬間はもうガックリだったけど、なおさら自分は好きな道を行くって決意しました。でも今思えば、そういう話をもっとよく聞いておけばよかったかなって思う。「音楽やるんだったら勉強しろ」って言われたしね”。
大学に行っても、六川の好奇心は擦り減らない。1970年代は、世界中から奇跡と呼ばれるほどの経済復興を遂げた日本に向けて、多くの海外アーティストが押し寄せた時代だった。六川は時間の許す限り観に行き、全身で本物のサウンドを浴び、帰ってきたら“復習”に励んだ。
“コンサートに行くと必ずプログラムを買って、穴の開くほど何度も何度も読むんです。今も捨てられずにいろんなプログラムを取ってあります”。
バイトでもらった給料は、ほぼレコード代とコンサート・チケット代に消えていったが、脳裏に焼きついたミュージシャンはどんどん増えていった。
才能を引き寄せる磁力
六川が行動的な人間であることは前述した。根底にあるのは、もちろん好奇心。だが行動に移すまでのハードルを押し下げていたのは、持ち前の外向的な性格だった。内向的でも周囲が放っておかない、いわゆる孤高のアーティストが音楽の世界には多いが、六川は少なくともそれとは真逆だった。
“僕はいろんなところに行って、いろんな人とワーワーやってるタイプだから、大学時代の軽音でも友達のいろんなバンドを観て回るのが好きだったんです。それで軽音ウエスタン所属の、スティール・ギターの駒沢(裕城)さんとも仲良くなれた”。
現在の六川は、仲間内ではベースだけでなく、オヤジギャグの名手としても知られている。警戒心を起こさせない人懐っこさは、六川に幅広い人脈を築かせた。そんな社交性という名の磁力のせいで、大学時代には多くの才能と惹かれ合い、触発し合う。
“たまたま才能のある人がいたっていう。そうじゃなかったら近づいていかなかったと思う”。
実際に大学時代に知り合った多くの友人がプロになっている。はちみつパイの駒沢裕城(steal g)しかり、一風堂の土屋昌巳しかり。六川がドラムではなく、ベースで参加したバンド、グレムリンは、のちに美乃家セントラルステーションに加入する土屋潔(g)や夕焼け楽団に加入することになる井ノ浦英雄(d)を擁していた。
“グレムリン時代に、ダニー・ハサウェイの『ライヴ』(1972年)に入ってる「ヘイ・ガール」をコピーしてね。メンバーみんなでサウナに行って、サウナのなかで口楽器の練習をやった。口楽器ってね、ドラムが「ドンドン」とか「タカドンドン」とか言って、ベースは「ドゥーン、ドゥドゥンドゥ」とか(笑)。土屋潔はギターだから「チャンカ、チャンチャン」とか口で言うの(笑)”。
フレーズを歌えれば弾ける、とはよく言うが、それを地でいくユニークな練習法だ。究極のイメージ・トレーニングとでも言えばいいのだろうか。
“今思えば、それがいい練習になった。手に負えなかったのはタワー・オブ・パワー。ベースがロッコ(プレスティア)だからねー。デヴィッド・ガリバルディ(d)とロッコのファンク・ビートには圧倒されました。このグレムリンをやってた頃ってのは、僕がミュージシャンになろうって決めた時期でもあった”。

いち早くプロになった先輩、駒沢裕城の影響も大きかった。駒沢のツテで見学したリハーサルが、あまりに刺激に満ちていたからだ。それは南佳孝のデビュー・アルバム『摩天楼のヒロイン』(1973年)のレコーディングのためのリハーサルだった。そこで細野晴臣のベースを聴いた衝撃で、プロへの思いは決定的になる。前年にリリースされ、話題になった『はっぴいえんど』を聴いて、それまで洋楽しか興味のなかった六川が、細野のベースだけは気になっていた。
“駒沢さんがプロになって、目の前で細野さんのベースを聴いたとき、ビート感がとにかくイカしてたんですよ。どうしてもベースに目と耳がいくんです。細野さん、すごかった”。
聴いているうちに六川は、自分の道筋を示されるような思いに駆られた。
“細野さんのベースには、オリジナリティって言うのかな、そういうものを感じて。グレムリンでは、タワー・オブ・パワーとかダニー・ハサウェイのカバーをやってたけど、もうカバーなんかやってる場合じゃないって。本当に。細野さんを見て、自分のスタイルを作らないといけないんだなって思い始めた”。