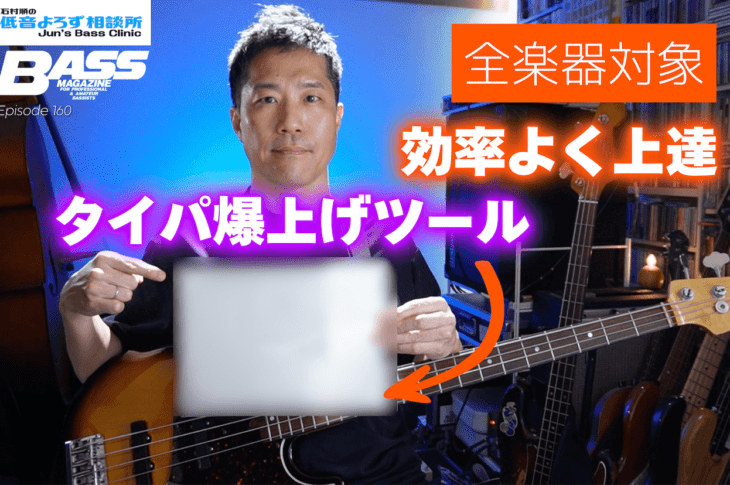NOTES

ベース・マガジン本誌にて好評連載中の『ニッポンの低音名人』では、毎回、日本の音楽シーンを支えてきた手練れたちの知られざるエピソードをお伝えしている。
現在発売中の2021年2月号では長岡“ミッチー”道夫が登場。
ここでは、本誌では紹介しきれなかったエピソードや関係者の証言、長岡のルーツや参加作を見ていこう。
習っても無駄!
長岡はギターもベースも、すべて独学だ。習う機会に恵まれなかったという以前に、試行錯誤しながら身につけるのが当たり前と思っていた。だから人から習おうという発想自体がなかった。中学のギター同好会が、互いに教え合ったりしない集団だったことも関係したかもしれない。“壁は自分で乗り越えるのが当たり前だと思ってた”という言葉がそれを物語っている。
とはいうものの、誰しも迷う時期はあるようで……。高校になり、久々に会った中学時代の同窓生が、やたらギターがウマくなっていたことに驚かされ、原因がクラシック・ギター教室と知り、教室を訪ねた。
“元同級生が「いい先生だよ」って言うから行ってみたんだよ。でも意味ないなって感じた。いろいろ教えてはくれたけど、自分で練習すりゃいいって思ったよ。習ってる時間が無駄に思えてね。なんかね、行ったらいっぱいヒントがもらえて、魔法みたいにウマくなるって想像してたけど、そうじゃなかったんだよ(笑)”。
同じことがのちにもあった。プロになってすぐ、ウッド・ベースを買ったときのことだ。レッド・ガーランド(p)のアルバムを聴いてポール・チェンバース(b)のプレイに憧れつつも、ジャズに対して恐怖心を持っていた長岡は、習うことによって、その恐怖心やコンプレックスが払拭できるかも、と考えた。
“結局、高校のときと同じだった。「弓はこうやって持つんだよ」とか教えてくれたけど、ぜんぜんピンとこなくて、それだけで終わっちゃった。もういいやって。家で譜面を見て練習すればいいって思った。僕は楽器については、習って習得するタイプじゃないんだね(笑)”。
良し悪しではなく、その人間のタイプによるのだろう。長岡は、頼りにできるのは自分の耳しかないことを、本能的に自覚していた。同時に自分が納得しないと行動しない頑固さがあった。
勘の良さと読譜修行
フレージングについても、ベースはコードのルート音を主とするフレーズを弾くことを、何とはなしに理解していた。
“だってコピーすると、そうなってるからさ。そのあとは、どのポジションで弾くかってことが気になってきた。まあそれは、ずいぶんしてからだけどね”。
技術面においても、独学で悩むことはなかった。ギターからベースに転向した者はピック弾きが多く、指弾きに戸惑う者が多いと聞く。しかし長岡は小学6年から中学の3年間クラシック・ギターを弾いていたので、指で弾くことには慣れていた。
“たまにピックで弾くこともあるけど、ピックだと空振りするんだよね(笑)。だから基本的には指で弾こうって。単純にそのほうがうまくいくからさ。それで実はポール・マッカートニーも指だと思ってた。だけど、よく見たら、あの人ピックだったんだよね(笑)”。
そしてもうひとつ。長岡には天性のリズム感があった。“道夫は私が預かって一人前にします”と両親の前で宣言した小野寺猛士(本誌2021年2月号参照)が惚れ込んだリズム感。小野寺はリズムにうるさいラテン・バンドのリーダーだったから、その見立ては確かだった。
“結局さ、ベースが自分に合ってたんだろうね。リズムっぽいのが楽しかった。ラテンのシンコペーションとかさ”。
しかし読譜となると話は別だ。それは知識ではなく訓練だからだ。知識で読み方は理解できても、スラスラ読みながらオンタイムで弾いていくには、それなりのトレーニング期間が必須だ。
それが偶然にも訪れたのは、大学1年の3月だった。ナイトクラブ、フロリダのハコバンからの誘いがそれだ。ビートルズなど、好きな曲を覚えて演奏するそれまでのスタイルから、弾いたこともない大量の曲を、譜面を見ながらプレイするという環境の変化。
客前で演奏するから、いったん曲が始まったら止めることはできない。大編成のバンドで、メンバーはすべて年上。しかもレパートリーの多くは、馴染みのなかったラテン・ビートの曲ばかり。
長岡は、限られた時間で譜面を読み、曲をこなしていくことを、このとき学んだ。お金をもらっている以上、甘えられないという意識もこのとき自覚した。それまでは周囲(そのほとんどは女性)から注目されるのが嬉しくてやっていただけだった。


好きなベーシスト
テクニックや知識はあとからついてきた。プロになってから出会い、感動し、吸収したベーシストのフレーズは無数におよぶが、長岡には、それら膨大なインプットのみならず、豊富なアウトプットの機会も用意されていた。スタジオ・ミュージシャンとして売れっ子になったからだ。ベース、それもエレクトリック・ベースの世界に多くの変革が起こった時期が、ちょうどこの時期(1970〜80年代)だったのも幸いした。
たとえばスラップ(チョッパー)奏法は、スライ&ザ・ファミリー・ストーンに在籍していたラリー・グラハム(b)が「サンキュー」(1969年)で用いて一般に知れわたり、その後1970年代にラリーがグループを抜けて作ったグラハム・セントラル・ステイションでの活動を通して浸透していったが、この時期長岡は、小野寺猛士とロス・オノデラスや森山良子のサポートなどで活動していた。
“プロになってからチョッパーが流行りだしてね。チョッパーってどうやるんだろう? って思ってたけど、音を聴いて自分が弾きやすいようにやってた。結局みんなそうなっちゃうね。そういや思い出したけど、『シティーハンター』ってアニメのテーマ(「City Hunter 〜愛よ消えないで〜」小比類巻かほる: 1987年)、あれチョッパーでやったよ。ディレクターから「これ、チョッパーでやって」って言われてさ、頑張ってやったんだよ”。
そして当時は、米国を代表するセッション・ベーシスト、チャック・レイニーが大活躍していた時期。多くのアルバムにチャックの名前がクレジットされ、長岡もそのうちのいくつかを好んで耳にするようになる。
“チャック・レイニーのプレイは好きだった。ああいう感じのフレーズは。派手なベース・ラインっていうか、ベースであんなことやってもいいんだ! って驚かされた。フレージングが多彩だよね。彼とは不思議な縁があって、アメリカと日本で会ってるんだ”。
そしてもうひとり長岡の耳を奪ったのが、ジャコ・パストリアスの完全無欠のベースだった。
“すごいなって思ったのはジャコだね。ジャズに少し興味が出てきた時期で、あんなプレイができたら、いいだろうなあって憧れたよ。でもねえ、あんなテクニックがあったら、ベースに転向しないで、今もギター弾いてたね(笑)”。