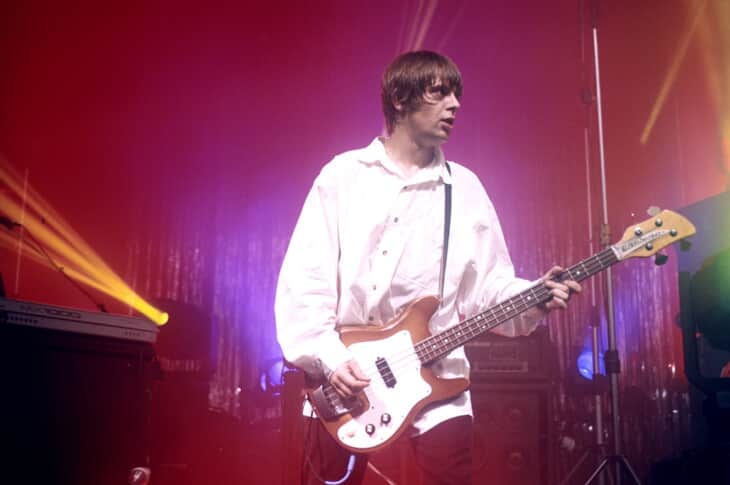PLAYER

UP
【ヴルフペック来日目前】知っておきたい、ジョー・ダートのベースが光る名演10選
- Text : Masamichi Torii
- Photo : Maryn Haertel
FUJIROCK FESTIVAL’25のヘッドライナーとして初来日を果たすヴルフペック(Vulfpeck)。現代ファンクのフロントラインを走るこのバンドにおいて、ベースを担うジョー・ダートの存在はまさに中核だ。跳ねるように動き回るフィンガリング、タイトで柔らかなロー・エンド、リズムの隙間を自在に泳ぐライン──時に主旋律を担い、時に全体を引き締めるプレイは、楽曲の設計そのものを支配していると言っていい。
ファンキーで、ユーモアがあって、それでいて緻密。ヴルフペックは、ベースが主役になり得ることを当たり前に証明してみせたバンドであり、その中心にいるのがジョー・ダートだ。そのグルーヴを、この夏ついに日本で体感できるチャンスが目前に迫っている。
本サイトの連載でもお馴染みの鳥居真道(トリプルファイヤー)が、ジョー・ダートの名演10曲を厳選。ライヴを前に、そのグルーヴの核心をあらためて確かめておきたい。
◎関連記事
1. Vulfpeck – Beastly(2011年)
ヴルフペックのデビュー曲。リーダーのジャック・ストラットンが友人の卒業制作に協力して、バンドをでっち上げ、曲を録音・録画してYouTubeで公開したところ、一部の音楽ファンから話題を呼んだ。とりわけジョー・ダートのプレイが与えたインパクトは大きかった。コピーしたいから音源を売ってくれという声も強かったそうだ。
「Beastly」は、ジョーのプレイをフィーチャーしたファンク・インストだ。巨大な岩が意思を持って自由に動き回っているかのようなベース・ソロは、それまでにありそうでなかったものだといえる。ベース史における重要度でいえば、ダニー・ハサウェイ『Live』収録の「Voices Inside(Everything Is Everything)」でウィリー・ウィークスが披露した長尺のベース・ソロに匹敵すると言っても過言ではない。ゴツゴツとしたトーンと気持ちの良い弾きぶりがジョー・ダートの魅力である。
2. Vulfpeck – Wait for the Moment(2013年)
カノン進行をベースに改造を施したゴスペル・フレイバーのネオソウル曲。ヴォーカルを務めるのはアントワン・スタンリー。シンプルかつミニマルなドラムのビートに対してジョーは、ディアンジェロ『Voodoo』におけるピノ・パラディーノを連想させるレイドバックした演奏を披露している。アーティキュレーションの付け方がネオソウル的だ。このようなアンサンブルを聴くと、その曲のグルーヴの質を決めるのはベースの役割なのだとはっきりすると思う。
曲の中盤でスタンリーが“ベースマン”と合図を出すと、ベース・ソロに突入。ジョーは鍵盤やギターなどのバッキングがない状態で、ささやかなソロを披露する。ルートやコード・トーンをふまえたシンプルなプレイだ。『Live at Madison Square Garden』収録のライヴ・バージョンでは、ジョーがひとりでソロを弾く場面がある。雄弁なプレイはその日のショーのハイライトのひとつだ。
3. Vulfpeck – 1612(2014年)
ミニマル、そしてロー・ボリュームというヴルフペック特有のスタイルを象徴する歌もの。ベースとギターがユニゾンで演奏するリフが、この曲の顔だと言って差し支えないだろう。ジーン・ナイトの「Mr. Big Staff」「Do Me」やステイプル・シンガーズの「I’ll Take You There」といった70年代スタックス・サウンドが参照されている。ヴルフペックのなかでもとりわけベースのコピーがしやすい曲だ。音が取りやすい分、ジョーがどのように音価コントロールをしているかという点に注目して演奏すると良いだろう。
曲の終盤では、指定のリフを崩して自由に演奏している。ファンクは基本的にフレーズの繰り返しで構成されている。それこそがファンクの魔力の源泉なのだが、人間は慣れると飽きてしまう生き物。ジョーのように曲のテイストを維持しつつ、ベース・ラインに変化をつけるのは、リスナーを飽きさせないためのテクニックのひとつだ。
4. Vulfpeck – Dean Town(2016年)
ウェザー・リポート「Tean Town」のパロディ的な曲で、ヴルフペックの代表曲のひとつ。ライヴでは、ファンたちがベース・ラインを大合唱するのが恒例行事となっている。そんな曲がいまだかつてあっただろうか。この曲のベース・ラインを考案したのは、鍵盤を担当するウッディ・ゴスだ。
「Dean Town」は、2フィンガーのオルタネイトで16分を刻み続けるパート、16小節にわたって繰り返しのない一筆書き的なベース・ラインのパートに二分できる。前者は、BPM109で16分を刻み続けるというほとんどベーシストの練習のために書かれたようなパートだ。
ヴルフペックのファンたちは、半音ずつ上昇したり下降したりするこのベース・ラインを大合唱するからすごい。しかしベース・ラインをコピーする際、先に音を取って歌えるようにしてから、運指を確認するほうが音楽的な学びが多いような気がする。ベース・ラインは積極的に歌ってみるのが良さそうだ。
5. Vulfpeck – Disco Ulysses (Instrumental)(2018年)
タイトルが示すように四つ打ちのディスコ・チューン。イントロにコリー・ウォンとセオ・カッツマンのギターの絡みをフィーチャーした曲で、ポップなコード進行にアース・ウィンド&ファイアー的なバイブを感じる。カッティングがメインのパートと、8分音符1個分シンコペーションする白玉系のパートで構成された曲だ。
ジョーは、前者ではギターのカッティングをボトムから強化するようなリフを演奏している。後者は、オクターブを上下するディスコ・マナーのベース・ラインでかつ、1拍目を毎回食うというせわしないプレイだ。しかし、言わずもがなの安定感があるので、決してごちゃごちゃした印象を与えない。さすがジョー・ダート。終盤では、例によってパターンを崩してアドリブっぽく演奏している。“始めにリズムありき”とでも言わんばかりに、グルーヴ=溝にはまった状態で演奏しているので、自由自在に演奏しても絶対にリズムがぶれない。体幹がしっかりしたベーシストだ。
6. The Fearless Flyers – Ace of Aces(2018年)
フィアレス・フライヤーズはヴルフペックの別働隊で、ジョー・ダートにコリー・ウォン、そして、スナーキー・パピーのマーク・レッティエリ、ネイト・スミスという腕利きたちで構成されたインスト・ファンク・バンドだ。ギター、バリトン・ギター、ベース、ドラムというすこし変わった編成になっている。「Ace of Aces」は彼らの名刺代わりになる曲だ。
曲の前半でジョーは、2本のギターの細かいカッティングにスペースを譲り、シンプルなプレイに徹している。しかし、後半に差し掛かるとスラップにスイッチ。スラップのフォームはレッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーと同じく親指が下を向くスタイルだ。スラップの合間に3連符を交えた高速パッセージを差し込んだり、プライマスのレス・クレイプールを彷彿させるパーカッシブな3連スラップを披露したりして、リスナーをハッとさせる。ジョーのプレイは、ベーシスト名鑑がそのまま血肉になっているかのようだ。
7. Vulfpeck – My First Car (Live at Madison Square Garden)(2019年)
2013年のEP『My First Car』の表題曲のライヴ・バージョン。元の音源ではハーモニクスを交えたパーカッシブな演奏だった。こちらのライヴ版ではベースが主役を張り、バンドをぐいぐいと引っ張る力強い演奏になっている。まるでクラビネットを弾いているかのようなプレイだ。ベースを使ってそんなことをする人に初めて出会った。
ド頭からジョー・ダートの本領発揮といった調子で、ボトムを支えつつ、アグレッシブに動き回る。アイアン・ジャイアントが全力疾走しているかのような躍動感だ。リーダー、ジャック・ストラットンがドラム・ソロを披露したのち、“ジョー・ダート・オン・ザ・ジョー・ダート”という中途半端な煽りを入れたのち始まるジョーのソロが圧巻。単に派手なだけではない。タイム感に躍動感がある。ちなみに、ジャックは“ジョー・ダート・オン・ザ・ジョー・ダート・ミュージックマン・ベース”と言いたかったのだと思われる。
8. Vulfpeck – 3 on E(2020年)
シック「Good Times」、クイーン「Another One Bites The Dust」、クール&ザ・ギャング「Hollywood Swinging」のベース・リフが、4弦開放のEを3度鳴らすものという共通点にあやかって書かれた曲だ。オタクっぽい小ネタを曲にしてしまうのがまさしくヴルフペック流だといえる。ライヴで「3 on E」を演奏するときは、アントワン・スタンリーとの掛け合いでこれら3つのベース・ラインが演奏される場面がある。ちょっとした遊び心だ。
ビート(=拍)に沿ってEを3発入れる。ものすごくシンプルな発想だ。問題は、それに対してどうリアクションするかである。ジョーは複雑かつとびきりファンキーなラインで、3発のEに自ら合いの手を入れる。これを演奏するときの左手の音価コントロールが凄まじい。歯切れが良いのでチューバのようにも聴こえる。ジョーのタイム感には粘っこいところがある。まさに下半身モヤモヤ。
9. Vulfpeck – Simple Step(2022年)
ボビー・コールドウェルやスティーリー・ダンのようなAORを彷彿させるビターで哀愁漂うコード進行は、ヴルフペックのイメージを裏切るものかもしれない。イントロでジョーは、歌心に満ちた情感あふれるハイ・ポジションのフレーズを挿入する。トゥーマッチな印象を与えてもおかしくないフレーズだ。しかし、エモーショナルに振り切きらず、ドライな仕上がりになっている。いい湯加減のフレーズだ。
ジョー・ダートのタイム感は、高速でブランコを漕ぐようなスイングがあるように思う。とりわけこの曲ではそれが顕著だ。ジョー特有のスイング感が出現する条件はなんだろうか。ビート=拍の長さが一定であること。音価コントロールにより緊張と脱力のメリハリを演出していること、右手も左手も指の動きが素早いこと。このあたりにスイング感の秘密がありそうだ。派手なソロが取れるベーシストは決して少なくない。ジョーが現代のベース・ヒーローたる所以は彼のグルーヴ感が飛び抜けて心地よいからに違いない。
10. Vulfpeck – New Beastly(2025年)
タイトルの通り、デビュー曲「Beastly」の新しいヴァージョンだ。ウッディがカウベルを一発叩くたびに客が歓声を上げるというヴルフペックらしいオフビートなユーモアが反映された曲だ。ウッディが茶目っ気を見せる一方で、ジョーはオリジナルの「Beastly」よろしく、現代のベース・ヒーローらしいプレイを堂々と披露している。
「New Beastly」は旧作と同様にテーマ部分とベース・ソロが交互に来る構成になっている。ジョーのソロは、アドリブながらも構成がしっかりしているから聴き応えがある。曲の中盤から始まるソロは、起承転結が明確だ。盛り上がりに山と谷があるので、ジョーのソロは、決してこれみよがしのテクニックを披露するだけの時間にはならない。客を湧かすためのソロになっており、奉仕の精神を感じずにはいられない。そして、ジョーのソロはいつも上機嫌だ。弾いている本人も楽しそうなのが良い。リズム面での遊びもおもしろい。
◎Profiles

ジョー・ダート●1991年4月18日、米国ミシガン州出身。幼少期からアース・ウィンド&ファイアーやタワー・オブ・パワーといったストレートアヘッドなファンク・ミュージックに傾倒する。ベースは7〜8歳の頃に弾き始め、中学では学校のジャズ・バンドに参加。その後、ミシガン音楽大学に進学し、ヴルフペックのメンバーと出会う。2011年に結成されたヴルフペックは、ロサンゼルスを拠点に活動するミニマル・ファンク・バンド。3月4日には、前作『Schvitz』から2年3か月ぶりとなる6枚目のフル・アルバム『Clarity of Cal』を発表。さらに今年の夏には初来日も決定しており、FUJI ROCK FESTIVAL’25で2日目のヘッドライナーを務める。
HP
鳥居真道(とりい・まさみち)●1987年生まれ。 “高田馬場のジョイ・ディヴィジョン”、“だらしない54-71”などの異名を持つ4人組ロック・バンド、トリプルファイヤーのギタリスト。現在までに5枚のオリジナル・アルバムを発表しており、鳥居は多くの楽曲の作曲も手掛ける。バンドでの活動に加え、他アーティストのレコーディングやライヴへの参加および楽曲提供、音楽関係の文筆業、選曲家としての活動も行なっている。最新作は、2024年夏に7年ぶりにリリースしたアルバム『EXTRA』。また2021年から2024年にかけて、本誌の連載『全米ヒットの低音事情』の執筆を担当していた。
X Instagram