PLAYER
過去を総括し、後進に未来を託すべく
すべてを出し切ったリーダー作
日本のジャズ界における最も重要なベーシストのひとりとして、長年にわたって渡辺貞夫グループのレギュラーや、大坂昌彦、小池修、青柳誠とのユニット“EQ”などでの演奏活動は言うに及ばず、『ジャズ・スタンダード・バイブル』や『ジャズ・スタンダード・セオリー』などの出版を通じて、しっかりしたジャズの基礎を伝える活動にも力を注いできた納浩一が、コロナ禍という、パフォーミング・アーティストにとって大きな逆境の最中、沈滞ムードを打ち破るかのような、力のこもった生涯最後のリーダー作『CODA』を完成させた。今回は、アルバムに注ぎ込まれたこれまでの経験や影響、サウンド作りのノウハウなどについて、本人にたっぷりと語ってもらった。
人生最後のアルバムと決めていて、
中途半端なものは作りたくなかった。
━━今回発表になった『CODA』の制作過程については、SNSなどの投稿でうかがっていました。その投稿だけを読んでも、自己名義としては最後のアルバムという覚悟のほどが伝わってきていました。その甲斐あってというか、アルバムは期待を上回るどころか、聴けば聴くほどいろいろな発見のある奥深い作品だという印象でした。
人生最後のアルバムと決めていて、中途半端なものは作りたくなかったので、とにかくすべての資材とエネルギーを投入しましたから、そう言っていただけるだけでもありがたいです。
━━ビッグ・バンドの曲は40代の頃に書いたそうですが、当時からビッグ・バンドのアルバムを想定していたんでしょうか。
具体的なアルバムを想定してはいませんでしたが、新宿にあるジャズ・クラブのSOMEDAYが主宰するビッグ・バンドのために何曲か書いてみないかと言われて、頭のなかにあったアイディアをビッグ・バンド風にまとめたことがあったんです。僕もジャコ・パストリアスのビッグ・バンドみたいなのを一度はやってみたいと思っていたので、書いておいても無駄にはならないだろうということでお受けしました。そのビッグ・バンドは10年ぐらいで活動が終わってしまったので、曲もそのまま本棚に仕舞いこんでいましたが、『CODA』のプロジェクトを立ち上げたときに、その頃に書いたビッグ・バンドの曲を一番の核にしようと決めたんです。
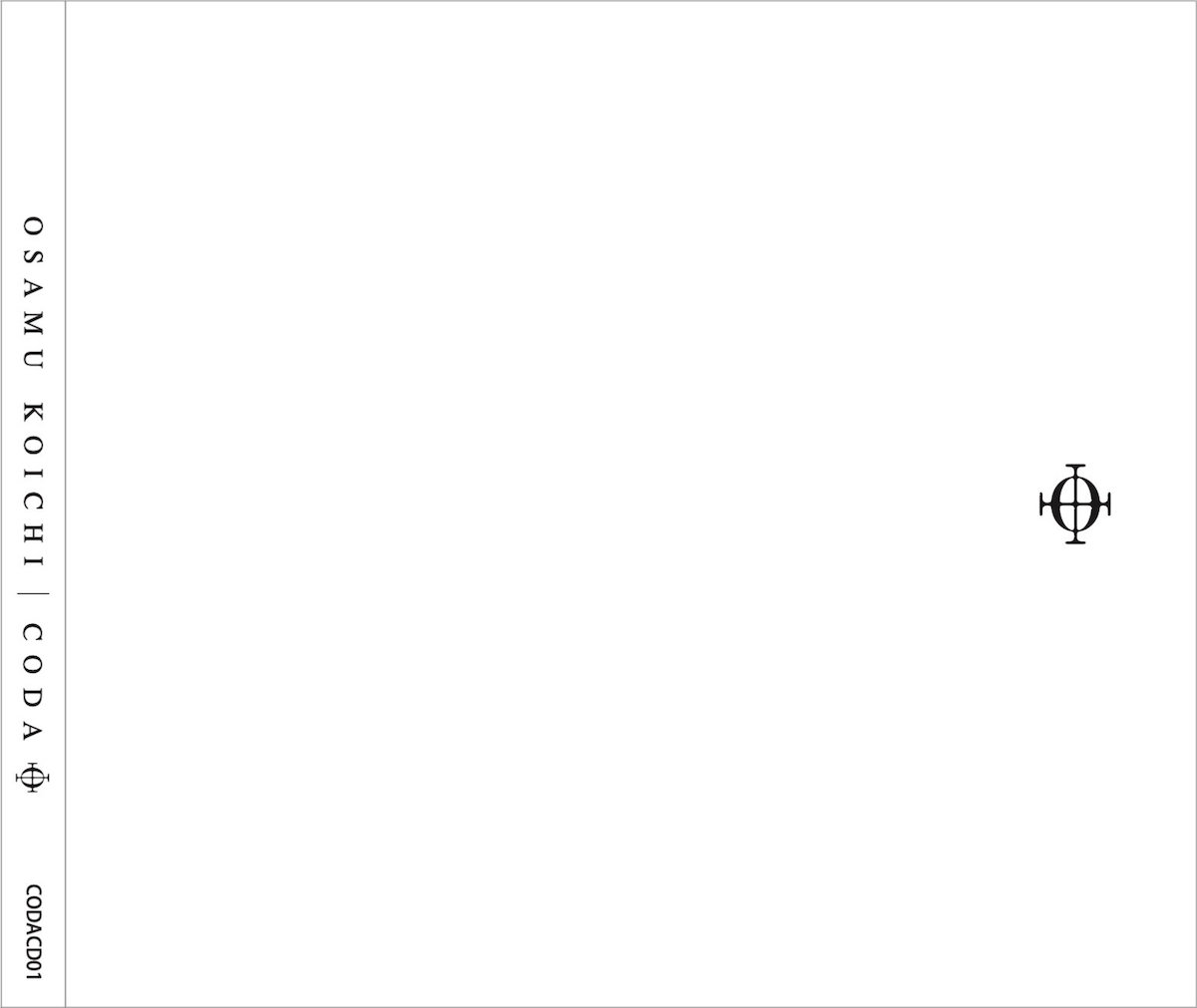
OSAMU RECORDS
Official HPやAmazonにて限定販売
━━ひと口にビッグ・バンドといっても、トラッドな書法ばかりでなく、いろいろな音楽の要素や工夫が盛り込まれていますね。
僕はビッグ・バンドの専門家ではないし、ビッグ・バンドの曲をちゃんと書ける人には勝てないので(笑)。だったらそれを逆手に取って、専門家が思いつかないような、ベーシストだからこそ作れるようなベースのアイディアを盛り込んだり、そのベースの動きに対してホーン・セクションをカブせたりしようと思ったんです。専門家じゃないと言っても、バークリー音楽大学時代からビッグ・バンドはイヤと言うほどやってきて、いろんな人のアレンジを研究したり、演奏する立場からスコアを勉強したりしていたので、その経験から学んだことをもとに誰もやっていない切り口を見つければ、それがオリジナリティにつながるんじゃないかと。ですから、ストレート・アヘッドなビッグ・バンドというのは最初から想定していなくて、特に則竹(裕之)君がドラムを叩いている曲(「Change The Rhythm」と「ひとりぼっちのジョージ」)なんかは、どちらかと言うと十何人のホーン・セクションのいるファンク・バンドみたいなイメージで書いています。「Milesmiles」はあえてストレート・アヘッドなアレンジにしましたが、「Cook Like Monk」と「三つの視座」はどこかひねってやろうと。僕は天邪鬼なので、どの曲も必ずひねりを入れているんですよ(笑)。
━━その言葉どおり、アルバムはひと癖もふた癖もありそうな「B.B.Groove」で幕を開けますね。ヘヴィなファンクに乗せてアップライトがソロを弾きまくるという……。
この曲はジャズ・ロックというか、レッド・ツェッペリンがジャズっぽくなって、ベースはジョン・ポール・ジョーンズの代わりにマーカス・ミラーとブライアン・ブロンバーグが入りました(笑)、みたいなイメージです。ツェッペリンやマーカスといった、単体で見れば二番煎じになってしまいそうな要素でも、それらを微妙にブレンドすると聴いたこともないような音になるんじゃないかっていうのが、この曲に限らずすべての曲に対する僕のアプローチなんです。
━━なるほど。
バリトン・サックスを使ったのも、生楽器のパワーやウネり、歌い方というのは、シンセでは絶対に表現できないと思っているからです。僕のなかでは、シンセを使った音楽って、いずれは消えていくというか、残らないような気がしているんですね。でも、特に僕らの世代がいまだにジャズやロックを好きで聴いていて、80年代以降のシンセがたくさん使われるようになった音楽を聴かなくなっているのも、やはり70年代以前の音楽には生の音があるからだと思うんです。それで、シンセでできるようなことでもあえて人間がやるようにしました。もちろん、ちょっとしたカラーリングでパッド系のシンセが入ったりするのはとても効果的でいいと思いますが、長く音楽をやっていると、やはり生身の人間がやるのが音楽の基本じゃないかというところに行き着くんですよね。
━━ビッグ・バンドの緻密なアレンジはどのように作業しましたか?
自分では打ち込みというのはまったくできないんですが、今だとパソコンで音符を書き込んでプレイバックすればある程度の音で確認できるので、アレンジしては聴き直すというのを何百回も繰り返しましたね。
━━Finale(※楽譜作成ソフトウェア)の再生機能を使う、みたいな?
そうです。で、ちょっとでも気になったりおもしろくないと思ったりした部分があれば、とにかく何十回でも聴き返して、上書きしていきました。
━━「Change The Rhythm」では2種類のテンポが変化しますが、仕掛けとしては最初のテンポの3連の音符4個分をもう一方のテンポにした感じでしょうか。
遅いほうの4拍子の2拍3連の3連符4つ分を倍にして速いほうのテンポにしています。ですから、速さの比率は2:3で、BPMだと遅いほうが100で速いほうが150になっています。数学的には合っていますが、譜面にしたり説明したりするのが大変でした(笑)。これは2000年頃に書いた曲で、その頃やっていたEQでも同じようなアイディアをおもしろがって試していたんですよ。
━━「空に虹を、地に向日葵を」ももともとEQのために書いた曲だそうですが、冒頭のコーラスは、ジェイコブ・コリアーを彷彿させますね。
コロナ禍の直前ぐらいに彼の来日公演を手伝ったことがあって、すごくおもしろいことをやっているなと思ったんですよね。彼はキーボードでああいうコーラスを作り出していましたが、4声、5声のホーン・アレンジの発想でもできるだろうと思って、ジェイコブっぽいアイディアを盛り込んでみました。日本ではあまりやっている人がいないし、肉声というのは圧倒的な存在感があって、それが入ることで音楽が分厚くなりますし。あと、和田明君というヴォーカリストと出会ったのも大きいです。いくらアイディアがあっても、できる人がいないとどうにもならないですからね。
━━で、あまり既存のものと比較するのも失礼かと思いますが(笑)、この曲の後半は、ペドロ・アズナールがいた頃のパット・メセニー・グループを思わせる、爽やかな雰囲気のサウンドになっていますね。
あれはもう、パット・メセニーと言われるのは覚悟のうえです(笑)。僕も彼のグループから多大な影響を受けているし、自分のなかから自然に出てきたものはそのまま自然にやっていこうというのが、今回の大きな考え方でもあったんです。2022年に自分のアルバムを出すなら新しい、今風なことをしなきゃならないんじゃないかと悩んだこともありましたが、最終的には自分のなかから自然に出てこないものを無理して作るよりは、これまでの経験を生かして自然に出てくるものをやろうと決めました。
━━確かに、ほかの曲にもいろいろな影響を感じさせる部分はありますが、むしろ、受けた影響を納さんのなかで見事に消化しているなあと思いながら聴いていました。この曲の出だしのハーモニクス奏法も、ジャコの「Okonkole Y Trompa」っぽいなと思ったり。
あれを聴いた瞬間から、自分でもやりたいと思ったんですよ(笑)。でも、あれをあのまま押し切ったら“ジャコやん”っていう話になるので、あれをチラッ、チラッとちりばめるだけで、ストーリーの骨格を違うところに持って行けばいいだろうと。そんな風に、思わずニヤッとしながら聴いてもらってもおもしろいかなということで、アルバム全体にわたっていろんな“隠しモード”を仕込んだというのはありますね(笑)。



