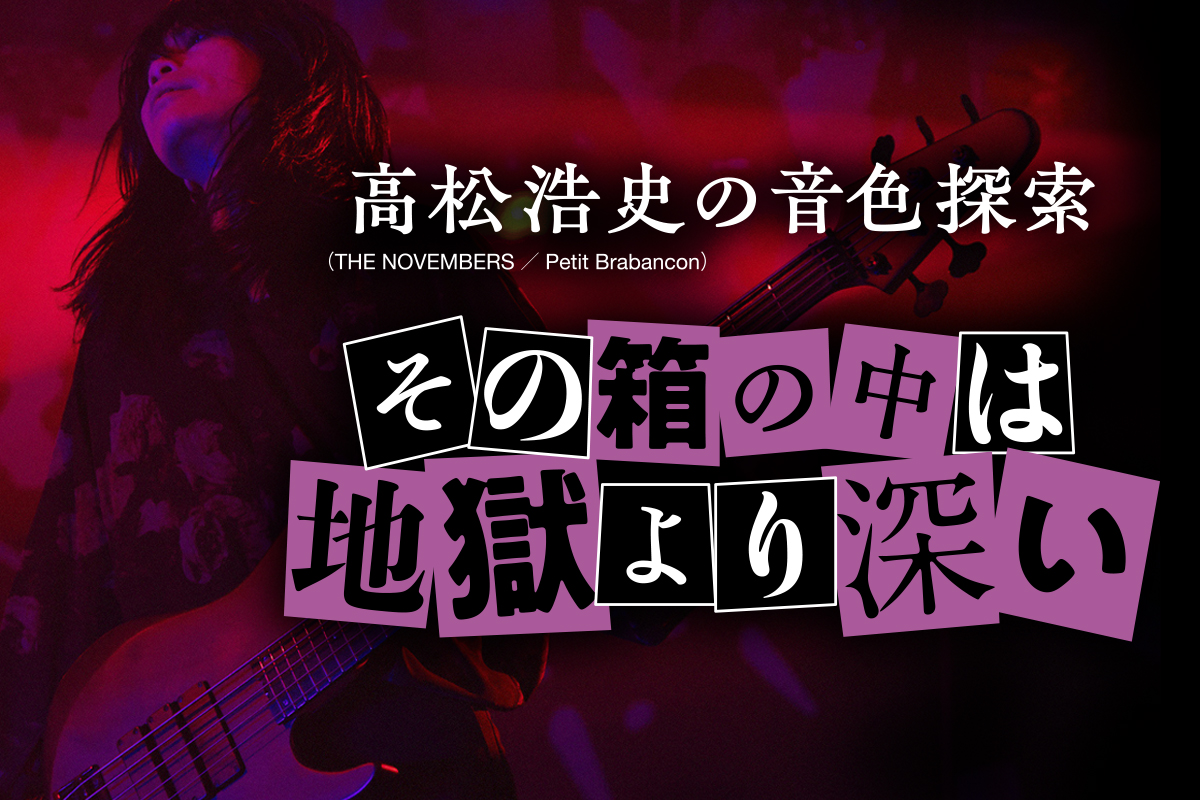NOTES
生粋のエフェクター・フリークとして知られる高松浩史(The Novembers/Petit Brabancon)による連載【その箱の中は地獄より深い】。マニアも唸るディープな分析から、ビギナー向けの実践的な解説まで、エフェクターの奥深い世界を独自の視点で掘り下げます。(連載一覧はこちらから)
今回は、3月にXで募集した「読者の皆さまからの質問」にお答えする回をお届け! たくさんのご質問をいただいたため、Part1, 2の2回に分けてお送りします。エフェクターのこと、ベースのこと、そして音作りのこと——リアルな声に高松さんが真っ向から答える、濃密Q&Aをお楽しみください。(編集部)
第20回(2025年3月篇):Q&A回答篇 Part1
Q:接続順などで音が変わると思うのですが、高松さんはボードを組むときにどういった手順、どういった工程を経て組み上げていますか?(質問者:まっすー)
質問ありがとうございます!
そうですね、おっしゃる通り、エフェクターは接続順でかなり音に影響が出ます。
僕がペダル・ボードを組む場合、まずは“どんな音を、どうしたいか”ということを考えます。例えば、“コーラスがかかった音を歪ませたい”とか、“最後にまとめてリヴァーブで余韻を残したい”などなど。そうすると自ずとある程度の接続順は決まってきますね。
歪み系に関しては、ゲインの低い順に接続することが多いです。最近はクリーン・ミックス(または原音ブレンドとも呼びますね)機能がついた歪みが多いので、例えばディストーションの前にオーバードライブを接続すると、“ディストーションだけの音”と、そこにオーバードライブがかかった音も混ざった“さらに少しゲインアップしたディストーションの音”、というようにゲインや質感のバリエーションを作ることができます。そういったところも考えつつ組んでいます。
こんな感じで考えていきますが、実際に音を出してみないとわからない部分もあるので、地道に“音出し→入れ替え”を繰り返してまとめていきます。機種の相性によっては、意外とディストーションのあとにオーバードライブという順番が良かったりすることもあるので……。
最後に、この質問の回答として一番言いたいことは、“エフェクターの接続順に決まりはない”ということです。人に迷惑をかけなければなんでもアリ。演奏者自身がかっこいいと思えたり、しっくりくればそれでオッケーなので、自分の感性を信じていろんな組み合わせを試してみてください。

Q:プチブラのベース音が大好きです! 1stアルバムの音作りや意識した音の帯域などを知りたいです!(質問者:dais)
質問ありがとうございます!
Petit Brabanconの1stアルバム(『Fetish』)はかなり歪ませていました。当時はSANSAMP、Darkglass B7K、ProCo RAT2なんかを組み合わせつつ音作りをしたと思います(それなりに昔のことなのでうろ覚えですが)。
ただ、これは夢を壊してしまうかもしれませんが、CDなどのスタジオ録音の音というのはミックス・エンジニアさんの影響が大きいです。エンジニアさんが全体のバランスを見て帯域などの調整をしてくれるので、実際に僕が作った音とは少し違います。
そのなかで僕が意識しているのは、バンド全体で鳴っているときのローやロー・ミッドの感じとか、どうしたらベースのフレーズが聴こえるかといったくらいでしょうか。こういったバンドなので、低音域はとても大事です。

本作についてのインタビュー記事はこちらから。
Q:高松さんは自身のバンド以外でもさまざまな場所で大活躍していますが、同じ現場でほかの方の機材も気になりますか? また演者同士で機材のお話をされていますでしょうか?(質問者:あすみ)
質問ありがとうございます!
そうですね、ほかの方がどんな機材を使っているか気になりますし、勉強になりますよね。ベーシストだけでなく、ギタリストの機材も気になるところです。機材のお話ももちろんします。人それぞれに考えがあって、おもしろいですよね。
Q:Petit Brabanconで5弦ベースをプレイされるお姿を拝見したのですが、 The Novembersで5弦ベースを使用されることはないのでしょうか?(質問者:ナカオ)
質問ありがとうございます!
必要であれば、というか、そういう曲ができたらThe Novembersでも5弦は全然ありえるでしょうね。ただ、現状では僕が5弦ベースの音域の曲を作るということは考えていません。楽器としては4弦ベースのほうが音は好きなので……あくまで、“今は”という感じです。
Q:飛び道具としてではなく、メインの歪みとして“歪みエフェクターの重ねがけ”をするアーティストが増えてきているように感じます。今後そのようなアプローチを積極的に検討する可能性はありますか?(質問者:WHARFIELD)
質問ありがとうございます!
何年も前からその手法は取り入れています。そのうえで、歪みの組み合わせでゲイン量や質感を調整するのは有用だと思います。
冒頭の回答でも紹介しましたが、例えば僕が使用しているディストーションはクリーン・ミックス機能がついているので、そこにオーバードライブがかかった音をミックスしたりしています。そうすると“ディストーションだけの音”と“少しゲインアップしたディストーションの音”のバリエーションができるので良い感じです。
ビット・クラッシャーの前段にディストーションをかけるとかなり良い質感のシンセ・ファズになるので、それもよくやる組み合わせです。
Q:現在の高松さんが思い描くノベンバでの音、プチブラでの音、サポート(健康、リメインズなど)での音、共通するものとそれぞれでの違いや意識する部分を伺いたいです。(質問者:miotoshi)
質問ありがとうございます!
Petit Brabanconだけ少し違うかなという感じでしょうか。ただ全プロジェクトで根本の部分は一緒ですね。
Petit Brabancon以外の各バンド・各プロジェクトではそこまで大きく音を変えることはありません。微調整程度ですね。そういった部分でPetit Brabanconだけ少し違うかなと。そもそも楽器が違うので。
“目指している音の方向性は違うけれど、意識や思想は一緒!”というイメージです。
Q::エフェクターのジャケ買いをされたことはありますか? あればそのときのエピソードお聞きしたいです。また、踏み心地のいいエフェクターがあれば知りたいです。(質問者:kim)
質問ありがとうございます!
個人的に、そのエフェクターに興味を持つきっかけは“見た目が良い”という部分がかなり大きいので、そういう意味では大体がジャケ買いですね。
基本的に踏んだときにテンションが上がるエフェクターをボードに入れているので、ボードに入っているものすべて良い感じです!
Q:機材に関する質問でなく、すみません。高松さんのピックですが、モチーフは何ですか? ずっと気になっています。(質問者:はみがきこ)
質問ありがとうございます!
タロットカードのデザインをモチーフにしています。かわいいですよね。

Q:普段ライヴで音を出すときに“楽器の棲み分けのためにEQのこの周波数はカットする、もしくは上げる”みたいな箇所はバンドによって変わったりしますか? そして、機材のどのポイントでそこを管理しているのか教えてほしいです。(質問者:Ren)
質問ありがとうございます!
音作り、どのバンドも大体同じ感じです。僕はプリアンプでSANSAMP BASS DRIVER DIという機種を使用しているのですが、そこで音を作っています。これをかけると基本のキャラクターが僕の思う“良い感じのベースの音”になってくれるんですよね。
具体的に言うと、ミッドはいらないところをカットしてくれて、ローは良い感じのところが上がってくれます。それに歪ませることもできるので、ほんの少し歪ませています。
ミッドの出方はブレンド具合で調整して、サンズアンプ臭くなりすぎないようにしています。ですので、サンズアンプがざっくり棲み分けしてくれちゃっているという感じですね。

Q:“曲のポイントで、元の音に少し歪みを足したいとき”に使用するのに最適な歪みエフェクターを教えていただきたいです。(質問者:米)
質問ありがとうございます!
“少し”がどのくらいか人によると思いますので、一般的なオーバードライブくらいで考えると、最近はこの連載でも取り上げたことのあるKarDiaN Serotonin Origin S.T.がお気に入りです(第16回をご覧ください)。僕が使用しているのはADD CBFというクリーン・ミックス機能がついたバージョンで、ベースにはこちらがおすすめです。
あとはPGS ADVENT / MONOLITH.という僕が監修させていただいた機種もおすすめです。音が太いです!
Q:私は[Alexandros]の磯部寛之さんに憧れていて、彼と同じTech21 / Red RipperとCrews Maniac Sound / SVD-001を手に入れたのですが、いまいちうまく使えていません。初心者がエフェクターとうまく付き合っていくにはどんなことをすればいいでしょうか? ツマミの位置とかに悩んでしまいます。(質問者:逆わたがし)
質問ありがとうございます!
エフェクターって使うのが難しいですよね。いただいた質問内容とは少し離れますが、まず大前提として、エフェクターをオフにした状態で音を出してみて、その音に対してエフェクターを使用して“どんな音にしたいのか”を想像すると良いと思います。エフェクターに関わらず、音作りで僕がやっていることです。すると必要なものが見えてきます。逆に“このエフェクター、いらないな”となることもあると思います。
いただいた質問内容に戻ります。
エフェクターを使用するときに、エフェクターはオフの状態で、コントロールをヴォリューム0、ほかは時計12時方向にします。次にエフェクターをオンにします。そのままだとボリュームが0なので音は出ません。ここで少しずつヴォリュームを上げていきます。エフェクターをオン/オフしながら、オフの状態と聴感上の音量をそろえていきます。僕はその音がそのエフェクターの基本的なキャラクターだと思っています。そこから自分が“こうなってほしいな”と思う音に近づけていくように調整していきます。
具体的には、SVD-001はとても素直なのでゲインを9時くらいにして、ロー・ゲインのオーバードライブとして使うのも良さそうですね。TREBLE、MIDDLE、BASSは必要がなければ真ん中で大丈夫です。少しカリカリと硬い感じがするなと感じたらTREBLEを下げたり、BASSを上げたりしてみてください。少しずつで大丈夫です。MIXは歪み側に振り切りで、フレーズが見えにくいと感じたらクリーンをミックスしてあげると良いと思います。
Red Ripperはファズですね。どちらかというとここぞというときにオンにして派手にするタイプのエフェクターです。特徴的なのはr.i.p.コントロールでしょうか。これは左に振り切りでスタートすると良さそうです。そこから少しずつ回して、好みのポイントを探ってみてください。
以上、一例です!
僕だったらこうするという感じで、そもそも音作りに正解はありませんので、自由に楽しんでみてください。あなたが気に入ったり、かっこいいなと思う音にできればまずはそれで大勝利です。具体的にバンドにどう合わせていくかはその後考えれば良いので。
参考になれば嬉しいです。
Q:ベース単体で気に入った音が作れたあと、バンドで合わせたときに“なんか違うな”と感じたときに、何から調整していいか迷子になってしまいます。例えばThe Novembersのような轟音のなかで、自分のイメージ通りのベース音を出すとしたら、音作りの際に何に注意したら良いでしょうか?(質問者:匿名希望)
質問ありがとうございます!
これはあるあるですよね。ベースだけで聴くとかっこいい音でも、バンドのアンサンブルに混ざると埋もれて聞こえなくなってしまったり。
これは回答が難しいですね。ライヴでもレコーディングでも、エンジニアさんによるミックスがどうなっているかが大きな点だと思うので、基本的にはエンジニアさんと話し合いながら決めることが多いです。その上で僕はハイが出過ぎないようにすることが多いです。ベースの重心を下げてあげるというか。ローからロー・ミッドのあたりがしっかり出るような音作りをイメージしています。
基本的にどんなアンサンブルでもその辺がしっかりしていれば大丈夫だと信じています!
あとはピッキングも重要です。音作りが良くても、ピッキングがしっかりしていないと台無しになってしまいます。なのでぜひその辺りも意識してみてください。
お望みの回答になっているか心配ですが……。
Q:ベースを始めて3ヵ月です。高松さんは普段どのようにベースの練習をしていますか?(質問者:ヲユ)
質問ありがとうございます!
練習……最近は近くライヴがあるプロジェクトの曲を練習する感じですね。毎月何かしらあるので。練習だけの練習みたいなことはしていません。
僕が初心者の頃はひたすらコピーをしていました。タブ譜を見つつ。逆にリズムの練習などはしたことがなく……。やはり曲で練習したほうが楽しいですからね。楽しく練習するのが一番です。実際に昔コピーした曲を聴くと、当時の自分は細かいところを全然コピーしきれていなかったなと思うことが多いです。でもそれでオッケー。好きな曲を大体の感じで弾けるようになれば御の字です。そこから少しずつ学んでいけば良いと思います。まずは成功体験!
ということで好きな曲のコピーはおすすめです。できれば耳コピが良いですが、タブ譜を見ながらでも良いと思います。
◎Profile
たかまつ・ひろふみ●栃木県出身。2002年に高校の同級生だった小林祐介(vo,g)とともに前身バンドを結成する。2005年からThe Novembersとしての活動を開始し現在までに8枚のフル・アルバムなどを発表している。2021年からは京(vo)、yukihiro(d)を中心としたプロジェクトPetit Brabancon、浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSのメンバーとしても活躍している。その他、Lillies and Remains、圭、健康のサポート・ベーシストも務めている。Petit Brabanconは8月7日に2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』を発表している。
◎Information
高松浩史 X Instagram